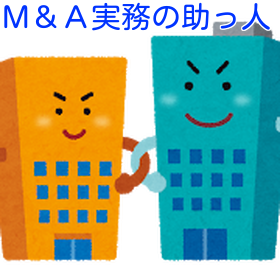目次
企業価値評価の概要
企業価値評価には、株価算定・株主価値評価・バリュエーション・会社のお値段査定など、様々な呼び方があります。
要するに、「買収価額はいくらなの?」ということを明らかにすることです。
M&Aも一種の商取引ですので、「お互いの合意した価格」が譲渡価額です。
ペットボトルのお茶を、150円で買おうが、10円で買おうが、1,000円で買おうが、契約当事者が納得していれば問題がないのと同じです。
相続税のように、法律において株価が決められているわけではありません。
とはいえ、買手は低い売却希望価額を提示し、売手は高い売却希望価額を提示するのは当然です。
これでは、いつまでたっても、価格交渉は折り合わず、M&Aが進まないことになってしまいます。
そこで、譲渡価額の計算根拠および計算方法を共有し、価格の目安を設定することで、具体的な価格交渉をしているのです。
たとえば、売手が1億円と主張し、買手が1,000万円と主張していたとします。
この根拠が「なんとなく」であれば、どのように交渉してよいのかわかりません。
しかし、たとえば、「DCF法(評価方法のひとつです)で、将来キャッシュフローが1,000万円で、割引率が10%だから、1億円」という売手の根拠が示されれば、「いやいや、将来キャッシュフローは100万円だから、評価額は1,000万円でしょう」と具体的に交渉しやすくなります。
とはいえ、企業価値評価の方法が1つだけであれば簡単なのでしょうが、実際には多くの評価方法があり、「唯一絶対の評価方法」はありません。
DCF法、類似業種比準法、年買法などがメジャーな評価方法です。
これら3つの評価方法については、のちほどそれぞれ別の記事で説明します。
場合によっては、配当還元方式、純資産法、再調達原価法などの方法が用いられる場合もあります。
最後に、しつこいですが、理解しておかなければいけないのが、評価額はあくまで「目安」であって、これによって譲渡価額を決定しなければいけないわけではありません。
譲渡価額はあくまで、「売手と買手が合意した価格」です。
企業価値評価報告書
企業価値評価に関しては、公認会計士などの専門家に「企業価値評価報告書」を作成してもらうのが一般的です。
企業価値評価報告書は、交渉においては重要な役割を果たします。
提示した価格が、「理論的、客観的、妥当な」価格であると、より説得力を持って示せた方が有利に交渉を進めることができるのです。
さしずめ、優秀な弁護士を雇った方が、裁判を有利に進められるのと同じです。
交渉以外にも、企業価値報告書が必要な場面があります。
1つめは、社内での説明のためです。
大企業にあっては、M&Aは経営企画部のサラリーマンが実施しており、上司、取締役の承認が必要で、M&Aに失敗した場合には、会社は株主訴訟を提起されるリスクがあります。
そこで、独立第三者の専門家が作成した企業価値報告書を入手することにより、論理的かつ客観的に充分な検討を実施した証拠を残すのです。
2つ目は、監査法人への説明のためです。
上場会社や上場準備会社、会社法上の大会社は、監査法人の会計監査を受けています。
お客様の会社でM&Aが実施されると、監査法人の仕事が増えます。
なぜなら、M&Aによって計上された無形固定資産の「のれん」の評価をして、減損が必要かを判断しなければいけなくなるからです。
このときに、買収価額のエビデンス(証拠)として、第三者の企業価値評価報告書を提出します。
3つめは、税務当局への説明のためです。
さきほど、譲渡価額は「当事者の合意」で決まると何度も説明しました。
そして、第三者間取引は、経済合理性を追求した結果として尊重され、税務当局はその取引価額に干渉できないのが原則です。
しかしながら、なかには、経済合理性を追求しているのか、疑わしい取引もあります。
たとえば、グループ会社間での取引価額を調整することにより、利益を付け替えている場合などです。
著しく時価と乖離する取引については、たとえ、第三者間の取引であっても、贈与税などが課されるリスクがあるのです。
そこで、譲渡価額が「時価」であるということを証明するために、第三者である専門家が作成した企業価値報告書を提示するのです。
まとめ
買収価額はあくまで「当時者の合意」で決まるが、DCF法、類似業種比準法、年買法などのメジャーな評価方法が複数ある。
説得力のある「企業価値評価報告書」を作成できるかがM&Aの交渉を有利に進めるポイントである。
交渉以外にも、社内説明、監査法人対応、税務当局対応など、報告書が必要な場面がある。
関連する個別具体的なお悩み解決サポート業務