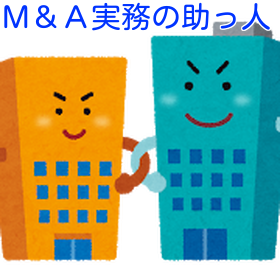目次
類似業種比準法とは?
類似業種比準法は、評価対象会社の業種と類似する上場企業(ベンチマーク)の株価をモデルに見立てて、利益・純資産などの項目で比較して株式価値を算定する方法です。
要するに、トヨタの株価が1株5000円なら、その1/10の規模の非上場自動車メーカーの株価は、取引所はないけど、だいたいトヨタの1/10で500円だよね、ということです。
具体的に見てみましょう。
A社の概要は以下のようになっていたとします。
| A社の純利益 | 10百万円 |
| 株式数 | 10千株 |
同業の上場企業B社の概要が、以下のようになっていたとします。
| B社の純利益 | 500百万円 |
| 株式数 | 100千株 |
| 株価 | 50,000円 |
まずは、A社とB社の一株当たり利益(PER)を求めます。
A社 10百円 ÷ 10千株 = 1,000千円/株
B社 500万円 ÷ 100千株 = 5,000円/株
次に、A社とB社のPERと、B社の株価から、A社の株価を求めます。
50,000(B社の株価) ÷ 5,000円(B社のPER) × 1,000円(A社のPER) = 10,000円
A社の株価は10,000円となります。
これは、A社のPERはB社の1/5のなのだから、A社の株価もB社の1/5の10,000となる、というイメージです。
最後に、1株当たり株価に株式数をかけて、株主価値を算出します。
10,000円/株 × 1,000株 = 100百万円
よって、A社の買収価額は100万円になります。
類似業種比準法は、株式市場での株価、という第三者取引をもとに算出される価格ですので、非常に説得力があり、理論的にも納得できる評価法です。
類似業種比準法の欠点
では、類似業種比準法で、上場企業の株価をもとに評価すれば問題がない、と思われるかもしれません。
しかし、欠点もあります。
一番大きな欠点が「はたして、本当に類似の上場企業(ベンチマーク)など存在するのか?」ということです。
とくに、ベンチャー企業などで、これまでにないサービスや製品を提供している企業は、ベンチマークがありません。
また、様々な事業を営んでいる場合(たとえば、ホームセンターを運営しながら、かつ丼屋も運営しているなど)など、複数の上場企業をベンチマークにして組み合わせるしかありません。
このような企業であればベンチマークが存在しないことがわかりやすいですが、一般の企業であっても、まったく類似の企業など存在しません。
企業はすべて、「世界に一つだけの花」なのです(笑)。
この曖昧なベンチマークの選定によって、株主価値は大きく変わってしまうのです。
また、上場企業に類似するような大手の非上場企業企業であればともかく、中小企業の株価を、上場企業の株価をもとに考えるのは、違和感がないでしょうか?
ですので、たとえば、「非流動性ディスカウント」などの概念を導入して、評価額を修正することもあります。
「非流動性ディスカウント」とは、非上場会社であり、株式を容易に換金できないため想定するディスカウントです。
とはいえ、このようなディスカウントを導入したとしても、根本的な解決にはなっていないように感じます。
DCF法よりは直観でも理解しやすいですが、やはり違和感が残ります。
続いて、どのような基礎データを用いて計算するか、によっても結果は変わってきます。
先ほどのA社の例では、一株あたり純利益(PER)を用いました。
しかし、他にも、一株当たり純資産(PBR)や、EV(企業価値)/EBTDA(償却費控除前税引後利益)倍率など、用いる指標もいろいろあります。
また、「株価」と言っても、前日の株価なのか、1か月平均株価なのか、6か月平均株価なのかで、株価も変わってきます。
やはり、計算の恣意性を排除することはできないのです。
とはいえ、繰り返しになりますが、大企業のM&Aにおいては、上司、取締役、株主に「理論的に」「客観的に」説明することが重要です。
ですので、DCF法同様、類似業種比準法で理論的に考えることは、避けることはできません。
まとめ
類似業種比準法は、類似業種の株式市場での株価をもとに計算する方法であり、説得力があり、理論的にも納得できる評価法です。
DCF法に比べて、直観的に理解しやすいですが、やはり違和感は拭えず、恣意性も介入してしまうのです。
関連する個別具体的なお悩み解決サポート業務