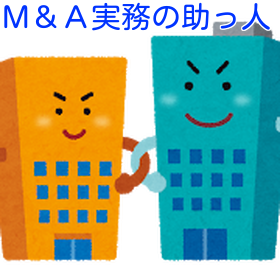今回はDCF法について説明します。
目次
DCF法とは?
DCF法(Discounted Cash Flow 法の略)は、将来会社が獲得すると期待されるキャッシュフローを一定の割引率で割り引くことによって、企業価値を算定する方法です。
あまりピンと来ないと思いますので(笑)、具体的に見てみましょう。
A社に関するデータが以下であるときに、DCF法でA社の企業価値を求めてみましょう。
| A社の将来キャッシュフロー | 100百万円 |
| 割引率 | 10% |
| A社の借入金(有利子負債) | 300百万円 |
| A社の事業以外の資産(現金含む) | 50百万円 |
この場合、まずは、将来キャッシュフローを割引率で割り引いて、事業価値を求めます。
100百万円(A社の将来キャッシュフロー)÷10%(割引率)=1,000百万円
次に、事業価値に、事業以外の資産を加えて、企業価値を求めます。
1,000百万円(事業価値)+50百万円(A社の事業以外の資産)=1,050百万円
企業価値から、借入金(有利子負債)を控除して、株主価値を求めます。
1,050百万円(企業価値)-300百万円(A社の借入金)=750百万円
よって、A社の買収価額は750百万円となります。
DCF法のイメージとしては、企業が将来に獲得するキャッシュが事業の基本的な価値であり、それに事業以外の価値を加算すると、企業全体の価値だよね。
とはいえ、企業全体が株主のものではなく、金融機関への借入金返済後の企業価値だけが、株主のものだよね、という感じです。
DCF法は、ファイナンス理論の観点からは、非常に理論的な企業価値評価方法である、という利点があります。
DCF法の欠点
DCF法は、理論的であるし、計算も簡単であるし、DCF法で企業価値評価をすれば問題ない、と思われたかもしれません。
しかし、実はそれほど簡単ではありません。
まずは、「キャッシュフロー」とは何でしょうか?
営業利益や経常利益、税引後利益とは違うのでしょうか?
キャッシュフローとは、要するに、「現預金」の増減です。
会計上の利益とは異なります。
たとえば、機械の減価償却費について考えてみましょう。
✕1年期首に新しい機械を100百万円購入し、新製品の製造・販売を開始したとしましょう。
機械の減価償却は、通常は定率法ですが、わかりやすくするために、定額法5年で償却したとしましょう。
この場合の会計上の利益とキャッシュフローの関係は以下のようになります。
| 年度 | ✕1 | ✕2 | ✕3 | ✕4 | ✕5 |
| 利益 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| キャッシュフロー | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金自体は、✕1年度にすでに支払っていますが、減価償却はその後5年間に分割して計上されます。
しかしながら、✕1年から✕5年までのトータルで見れば、利益の合計も、キャッシュフローの合計も100で一致します。
今回は、税金を考慮していませんが、税金を考慮するとより複雑になります。
キャッシュフローの計算方法を理解したところで、考えてみてください。
「将来のキャッシュフローなんて、どうやって、予測するのか?」と。
あなたの会社は、これから将来5年間に、いくらのキャッシュフローが計上できるか、考えてみてください。
そして、その根拠を示してみてください。
もしも、あなたの会社が事業計画を作成しているならば、過去の事業計画を引っ張り出して、実績と比較してみてください。
計画と実績が完全に一致していることなど、ありえないはずです。
つまり、将来キャッシュフローの見積もりには、不確実性が大きく介入してしまうのです。
たとえば、先ほどのA社の例で、A社の将来キャッシュフローを200百万円と見積もった場合、A社の株主価値は、1,750百万円となります。
逆に、50百万円と見積もった場合、250百万円となります。
将来の見積りによって、買収価額は大きく変わってしまうのです。
次に、「割引率」について考えてみましょう。
そもそも、「割引率」とは何でしょうか。
ざっくり言うと、リスクが高ければ割引率が高くなり、リスクが低ければ割引率は低くなります。
たとえば、あなたがトヨタ自動車の株式を購入する場合、トヨタは会社自体が信頼できるし、将来のキャッシュフローもそれほど予測からは乖離しないだろう、と思うことでしょう。
よって、トヨタの割引率は低くなります。
逆に、あなたが先月設立されたベンチャー企業の株式を購入する場合、ベンチャー企業自体が明日倒産するかもしれないし、将来のキャッシュフローの予測なんてあてにならない、と思うことでしょう。
よって、ベンチャー企業の割引率は高くなります。
さて、では、買収する予定の会社の割引率は、どのように設定すればよいのでしょうか。
これもキャッシュフロー同様、見積りであって、不確実性が大きく介入します。
たとえば、さきほどのA社において、割引率が5%見積もった場合、A社の株主価値は、1750百万円となります。
逆に、20%と見積もった場合、250百万円となります。
割引率の見積りによって、買収価額は大きく変わってしまうのです。
しかも、割引率とは、正式なファイナンス理論では、「加重平均コスト(WACC)」のことです。
WACCの計算式は以下のようになります。
加重平均コスト(WACC) = Rd (1 – t) × D ÷ (D + E) + Re × E ÷ (D + E)
- Rd(負債コスト)
- t(実効税率)
- D/Eレシオ(資産負債比率)
- Re(自己資本コスト)
頭が痛いですね(笑)
しかも、これだけでは終わりません(笑)
自己資本コストは、CAPM(資本資産価格モデル)で以下の式で求めます。
Re = Rf + β × (Rm – Rf))
- Rf(リスクフリー・レート)
- β(ベータ)
- Rm- Rf(マーケット・リスク・プレミアム)
そして、βとは、、、マーケット・リスク・プレミアムとは、、、と続くわけですが、もうお腹いっぱいでしょうから、止めます(笑)。
要するに、マニアックなファイナンス理論と、多くの見積りを介入させなければ、割引率を理論的に計算することはできないのです。
しかも、「将来キャッシュフロー」を「割引率」で割り引くことによって、「企業価値」を求める、というのは、数学的には、ファイナンス理論的には正しいことが証明されています。
しかしながら、「直観的に」理解できる人はほぼいないのではないでしょうか。
ましてや、ファイナンス理論に触れたこともない中小企業の経営者が理解できるはずもないですし、はっきり言って理解する必要もありません。
そんな時間があるなら、本業にもっと力を入れるべきです(笑)。
とはいえ、大企業のM&Aにおいては、上司、取締役、株主に「理論的に」「客観的に」説明することが重要です。
ですので、DCF法で理論的に考えることは、避けることはできません。
まとめ
DCF法は将来キャッシュフローを割引率で割り引く方法で、非常に理論的な方法です。
しかしながら、将来の見積りに不確実性が介入したり、直観で理解することが難しい、など欠点はあります。
関連する個別具体的なお悩み解決サポート業務